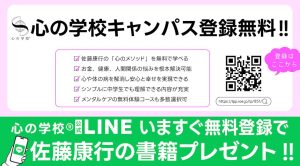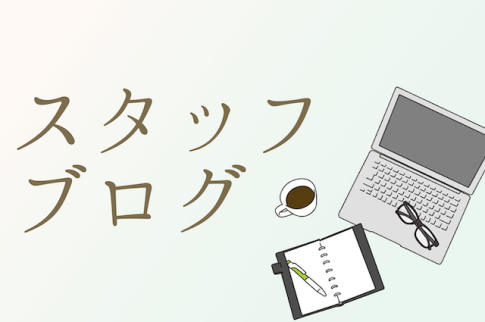※YSカウンセリングセンター監修
こんにちは。
心の学校オウンドメディア編集部です。
私たちは、日々、いろいろなストレスにさらされています。
経済的なこと、生活環境、健康、人間関係、期待やプレッシャー、急なトラブルや事件などなど。
その中でも特に、人間関係のストレスは、30代、40代の女性にとっては、とても身近で、より重く感じるのではないでしょうか?
なぜなら、家庭内の人間関係、仕事の人間関係、親戚やご近所さんとの関係から、子育て中の人はママ友や学校の先生との関係など、様々な役割を同時にこなさなければならないからです。
そして、心と体に様々な症状を引き起こします。
イライラ、不安、緊張、憂うつ、不眠、頭痛、胃痛、食欲不振などは、ストレスが原因で起こる代表的な症状です。
これらの症状は、ストレスに対する心と体の警告サイン。
放置すると、心身の健康を損なう恐れがあります。
そして、一旦ストレスを感じてしまうと、その後の人間関係にもますます影響が出てきてしまいます。
相手に対して攻撃的になったり、無視したりするなど、望ましくない行動をとってしまうことがあるでしょう。
この記事では、人間関係のストレスが引き起こす様々な症状や影響をみていきます。
人を悪く思うことの影響

人間関係のストレスを感じるとき、私たちは無意識のうちに相手を悪く思っているのかもしれません。
ストレスのきっかけは様々で、意見の不一致、誤解や、すれ違い、喧嘩、不公平、裏切り、信用できない、偏見、差別、役割分担の不均衡など、他にもいろいろありますよね。
なぜ、そう思ってしまうのでしょうか。
それは、人間には『批判精神』というものがあるからなんです。
この『批判精神』は、人間が進化し、生き残り、社会に適応し、成長していく上で必要なものでした。なので、批判すること自体は悪いことではありません。
バランスの取れた批判精神は、自己成長や社会の改善に貢献します。
ですが、他者への過度な批判や自己批判は、ストレスや不安を引き起こすことがあります。
ですので、批判精神を持ちつつ、肯定的、ポジティブな視点への切り替えが重要です。

批判にも種類があり、例えば、
・悪意のある批判や、非難
・自分を正当化するための批判
・柔軟に考えられなかったり、一つの考えに固執したり、誤解や曲がった解釈に基づく批判
などがあります。
相手から批判を受けた時は、単に「意地悪〜」と思うのではなく、どんな批判なのかを分析してみると解決の糸口が見つかることもあります。
ちなみに、
自分に向かう批判精神は『反省』になり、
他人に向かう批判精神は『批判』になります。
結局、人を悪く思ったり、心の中に批判精神があること自体が、自分にも人にも厳しくなり、ストレスになるということです。
人間同士はすべてつながっているので、周りの人を悪く思うと、自分も悪くなってしまうのです。
批判と忠告の違い

批判と似たものとして『忠告』がありますね。
「自分は批判してるんじゃなくて、忠告してるだけだよ」という人もいるでしょう。
では、批判と忠告の違いは何でしょうか?
忠告には『相手のことを思う』という愛の心があります。
一方で、批判の根底には愛が欠けています。
批判とは

批判は、誤りを指摘することや、改善点を明らかにすることが主な目的です。
批判者は問題点を指摘することに重点を置いてます。
その結果、相手が防衛的になったり、ネガティブな感情を抱いたりすることがほとんどです。
相手との関係が悪化したり、相手がやる気を失ったりする可能性が多いです。
内容は、批判者の価値観や基準に基づいて行われ、批判者の主観や期待が強く反映されることが多いのも特徴です。
忠告とは

一方で、忠告の目的は、相手が間違いや困難を避け、より良い結果を得るための助けを提供することです。
相手の感情や受け取り方を考えながら、柔らかく、前向きな方法でアドバイスを提供しようとします。
相手にとって無理難題ではなく実行可能で、役立つ提案をすることが重視されます。
忠告は、信頼関係を深めることができ、相手が「助けられた」と感じることで、ポジティブな結果をもたらします。
忠告するときは、相手の立場やニーズを考慮し、より客観的で相手に寄り添った形で提供されるのが特徴です。
このように『批判』と『忠告』は、目的も、伝え方も、結果も全く別物です。
愛の欠けた言動は、相手にも自分にもプラスになりません。
人に良くなってほしいと願うことは、自分も良くなることにつながります。
『与えること』と『受け取ること』は、同じだからです。
症状が出る前からのストレス解消を

自分でも気づかないうちに、ストレスは溜まるものです。
症状が出ていないと思われる普段から、自分に合ったストレス解消法を見つけ、自分がご機嫌な状態でいることも大切です。
あなたも、今までなんとなくストレス解消のためと思ってやっていることがあると思いますが、一つだけではなく何パターンか持っているのがおすすめです。
気軽にできる呼吸法や、瞑想から、隙間時間にできる運動やヨガ、週末にたっぷり時間を取る小旅行や趣味など、その時の状況、体力、資金力によってストレス解消法をカスタマイズしましょう。

好きなことに没頭する時間を作ることも効果的です。
没頭している時間は、『今』『ここ』に集中できるからです。
もちろんストレスの元がなくなるわけでもないし、問題が解決するわけでもないのですが、一旦ストレスから離れることで、気持ちにゆとりができたり、客観的に受け止められるようになります。
また、「人を責めずに、仕組みを見直す」という方法もあります。
犯人探しや、誰かのせいにするのではなく、そもそもその仕組み、やり方、ルールを変えた方がノンストレスでスムーズに物事が進む、という考えです。

他の解消法としては、一人で抱え込まずに、誰かに話を聞いてもらうのもいいでしょう。
ただ、身近すぎる人に話した場合、さらにストレスになる言葉を受け取ることもあります。そんな時も、自分のために時間を設けて聞いてくれるのですから、感謝の気持ちを忘れず、話し方に気をつけましょう。
身近な人には話しづらい、あるいは、聞いてくれる人がいない場合は、専門家に相談するのもおすすめです。じっくり聞いてもらえますし、新しい視点が得られることもあります。
疲れた時に体のマッサージや、メンテナンスをする感覚で、心のメンテナンスも行いましょう。
自分自身を大切にしよう

人間関係のストレスと上手に付き合うには、自分自身を大切にすることが欠かせません。
先ほど述べた『批判精神』の思考は、自分自身に対しても同じことです。
自分を批判することで、反省、自己嫌悪、自信喪失、自暴自棄などになります。
まずは、自分の湧いてきた感情や欲求に正直になり、それをいい悪いと裁かず、否定せずに受け止めましょう。
「あー、今辛いよね。〇〇だもんね」「これは寂しいよね」「これは心が痛いよね…」と自分の感情を抱きしめてあげましょう。
また、自分の良いところを認めることも大切です。
人と比べる必要もないし、完璧である必要もありませんので、今の自分の長所や努力を評価しましょう。
自分を認めることで、自信が生まれ、自己肯定感がアップします。と同時に、相手のことも、少しずつ認められるようになります。
そうして、人間関係のストレスにも強くなっていけるのです。
周りの人たちとの関わり方を見直そう

人間関係のストレスを減らすには、周りの人たちとの関わり方を見直すことも効果的です。
自分が、苦手と思っているということは、相手もそう思っている可能性もあります。
なので、相手の気持ちを尊重することも重要です。
具体的には、相手の生い立ちや、価値観、親との関係、トラウマなどの人生経験からその人の思考が形成されていますので、会話の中で何気なく聞いてみたりしながら、人間観察をしてみましょう。
よくよく話を聞いてみると「あ、過去にそういう経験があったから、そうしてるんだ」とか、「この人にとっては、この方法しかないと思ってるからあんなふうに言うんだな」などを会話から理解できると、関係性の見直しができたり何かしらの発見もあります。
その人とのストレスが大きくなって「すごく苦手…」「考えるのも嫌だな…」となる前に、興味関心を持って相手を知ることも大切です。
苦手になってから関心を持つのはとても大変です。

また、自分の思いを伝えることを恐れず、率直にコミュニケーションを取ることも大切です。
もちろん自分の思いを伝える時は、自分の表情や、声色、言葉のチョイスには少し気配りが必要です。
誤解のないように、相手の心に届くように工夫しましょう。
相手が心を開くには、まず自分から自己開示していくことです。
お互いの良いところを認め合い、支え合える関係を築きましょう。
いつでも心全開にする必要はありませんので、TPOに応じて程よい距離感でお付き合いできるといいですね。
まとめ:大切なのはそのストレス症状に気づき適切に対処を

人間関係のストレスは、私たちの心と体に様々な症状を引き起こします。
さらに、その問題に直接関係のないあなたの家族や、職場の人などにも影響を及ぼす可能性があります。
それは、イライラしてしまったり、疲れた様子で心配をかけたり、あるいは集中力が奪われ、うっかりミスにもつながるかもしれません。
大切な人と楽しい時間を一緒に過ごしたいのに、会う元気が出なかったり、会っても心の底から楽しめなかったり…
知らず知らずのうちにそんな影響も出てきます。
大切なのは、そのストレス症状に気づき、適切に対処することです。
最初に書きましたが、人間関係のストレスを感じるとき、私たちは無意識のうちに相手を悪く思っているのかもしれません。
そこをポジティブに切り替えて、その人に良くなってほしいと願うことは、巡り巡って自分自身の幸せにつながります。
与えることと受け取ることは、実は同じことなのです。
この真理を胸に、周りの人たちへの思いやりを忘れずに、豊かな人間関係を築いていきましょう。
まずは、自分自身を大切にしてください。
自分の感情や欲求に正直になり、自分のペースで生活することが重要です。
ストレスと上手に付き合いながら、自分らしく、豊かな人生を送ってください。
あなたの心が軽やかになりますように。
+*+*+*+*+*+*+*
もし、誰かに悩みを相談したいなら、YSカウンセリングセンターでしたら初回相談が無料です。お気軽にご相談くださいね。
初回無料相談LINE | YSカウンセリングセンター
+*+*+*+*+*+*+*