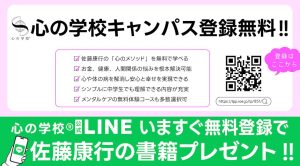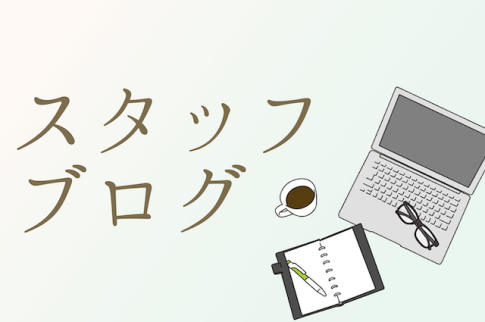※YSこころのクリニック監修
こんにちは。
心の学校オウンドメディア編集部です。
前回はうつ病で知っておきたい症状と7つのタイプ(中編)ということで、「季節性うつ病」と「産後うつ病」の症状などについてお話ししました。
今回は、その続き「子どものうつ病」「更年期うつ病」「老人性うつ病」と、番外編として「気分変調症」(持続性抑うつ障害)をご紹介します。
いったいどのような症状なのでしょうか?
一緒に見てみましょう。
前回までの記事はこちら→URL(サムネイルと冒頭部分の説明文が表示される予定)
5.子供のうつ病について

大人と違ってストレスを感じるという事が少ない子供は「うつ病にならない」と思われがちですが、実はそうではありません。
『子供もうつ病になります』
子供のうつ病の場合は発症する「きっかけ」があるのが多いといわれています。
そのきっかけというのは
・引っ越しや転校
・両親の離婚、再婚
・いじめ
・受験
などです。
こうしたきっかけから、子供も大人と同じように眠れない、食べれない、頭痛や腹痛を訴えるといった抑うつ症状が起こります。
また最近では発達障害の子どもも、周りとのコミュニケーションが取れないイライラや周りは出来るのに自分が出来ないというストレスから、うつ病になるというケースも多くなっています。
子供は大人と違って自分の抑うつ状態が分かっていませんし、それを上手く話せない事が多いです。
ですので、
「子どもの食欲が落ちている」
「子どもが学校や友達の話をしなくなった」
「子どもが夜、眠れていないようだ」
「登校前になると、体調不良を訴えるのが増えた気がする」
という様子が続くようでしたら、子どものうつ病の可能性もあります。
お子さんへの接し方に目を向ける

そして、子どものうつ病をとらえるうえで、大切な視点があります。
それは、親御さんの「お子さんへの接し方」に目を向けていくことが、お子さんの心の回復にとって不可欠だということです。
うつ病の心配から医療機関にかかると、お子さんのうつ病に対しても、一般的には抗うつ剤などの薬が症状に応じて処方されます。
薬はあくまでも対症療法です。子どもの心の中にある「うつの根っこ」を根本的に解消してくれるわけではありません。
うつ病になったきっかけは、学校生活や友人関係や家族との関係にあったとしても、その根底には、お子さんの自己肯定感や自尊心の低さがあります。
お子さんの自己肯定感や自尊心を引き出してあげられるかどうかは、親御さんの「接し方」にかかっています。
苦しむわが子を目の前にして、何とかしたいという思いから、親の考えを押し付けてしまっては、状況をますます悪くしてしまいかねません。
うつ病のお子さんへの「接し方」で一番大切なのは、子どもの言葉や考えを否定することなく、ゆっくりと聞いてあげることです。
そしてお子さんの素晴らしさに目を向けて、認めてあげることです。
決して焦らず、子どものペースを大切にしながら接していくことで、心は回復に向かっていきます。
わが子のうつ病が心配になったら、専門家に相談することが大切ですが、親御さんの接し方が回復のカギだということを忘れないでくださいね。
誤解されやすい『更年期うつ病』と『老人性うつ病』
うつ病と症状が似ているために、誤解をされやすく「医師も診断が難しい」というものに
・更年期うつ病
・老人性うつ病
があります。
6.更年期うつ病とは

更年期うつ病は、主に女性が閉経後で更年期と呼ばれる時期に起こるうつ病ですが、更年期障害の
・体の不調
・イライラや気分の落ち込み
という症状と、抑うつ症状が似ているので診断が難しいとされています。
そのため「更年期障害と言われて薬を飲んだり治療に通っているけど、一向に良くならない」という場合は、更年期障害ではなく更年期うつ病の可能性があります。
また、更年期障害は男性にも訪れます。
男性の更年期障害が起こる理由ですが、加齢とともに男性ホルモンの分泌が低下してくるためです。
「更年期障害かと思っていたらうつ病だった」という可能性も、もちろんあります。
男性更年期障害の場合は、夕方にかけての疲労感や気力の低下、肥満、頻尿が現れます。
一方、典型的なうつ病では、朝方に気力が低下して夕方になると元気が出てくる傾向があります。
朝方に気力が低下するという場合は、更年期障害と思いこまずに、うつ病を疑って心療内科を受診した方が良いでしょう。
7.老人性うつ病とは

次に老人性うつ病ですが、老人性うつ病と誤解されやすいのが「認知症」です。
老人性うつ病も更年期うつ病と同じように症状が似ているので、「認知症と診断されたけど、老人性うつ病だった」あるいは「老人性うつ病だと言われたけど、更年期障害だった」というケースが多いです。
老人性うつ病と認知症の違いというのは、老人性うつ病だと体の不調だけでなく、寂しさ・辛さという「心の抑うつ症状」をよく口にします。
しかし、認知症の場合は寂しさや辛さをあまり感じないので、この寂しさや辛さを口にする事はありません。
こうしたちょっとした違いを知っていれば、老人性うつ病か認知症かという初歩的な見極めが出来るようになります。
でも、だからといって素人目で判断して「医療機関の受診は、後日に」とすると、抑うつ症状を放っておいてしまうので、早期治療・回復が出来なくなります。
ですので、もしデイケアや高齢者向けの福祉サービスを利用していて、普段の様子を見ていて「あれ?」と思ったら、福祉サービスのスタッフさんに「最近、何だか体の不調や寂しさなどを話すんですよね」と相談してみるのもよいでしょう。
【番外編】抑うつ症状は軽いけど年単位で続いて、治りづらい『気分変調症』

最後は番外編となりますが、抑うつ症状は軽いものの年単位で続き、治りづらい『気分変調症』についてです。
「何をしても楽しくない」
「気持ちがひどく落ち込んだりなどはないけれど、いつも体調が悪い」
この「何をしても楽しくない」というのは抑うつ症状と似ていますが、『気持ちがひどく落ち込んだりなどはないけれど、いつも体調が悪い』というのが1年、2年という年単位でずっと続いていたら、それは『気分変調症』(持続性抑うつ障害)かもしれません。
気分変調症は会社で仕事をしたり、普段の生活を過ごせはするのですが、抑うつ症状がずっと続いているので、心が晴れる・スッキリする事がありません。
またうつ病に比べると、治療薬が効きづらいので治りづらいともいわれています。
気分変調症は「2年以上、体の不調や気分の落ち込みがずっと続いている場合」に、気分変調症と診断されるのですが、2年以下であってもこうした症状がある場合は早めに専門の医療機関を受診することをおすすめします。
これを「いつもの事だから」と気にせずにいると治療が行えず、治りづらさに拍車がかかる事になるかもしれません。
まとめ

今回はうつ病の7つのタイプの中から「子どものうつ病」と「更年期うつ病」「老人性うつ病」の症状について、そして番外編として『気分変調症』(持続性抑うつ障害)についてお話ししました。
今までお話ししてきたうつ病の7つのタイプにもし当てはまるようでしたら、すぐに専門家に一度相談することをおすすめします。
今回の記事が参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
+*+*+*+*+*+*+*
もし、誰かに悩みを相談したいなら、YSカウンセリングセンターでしたら初回相談が無料です。お気軽にご相談くださいね。
初回無料相談LINE | YSカウンセリングセンター
+*+*+*+*+*+*+*